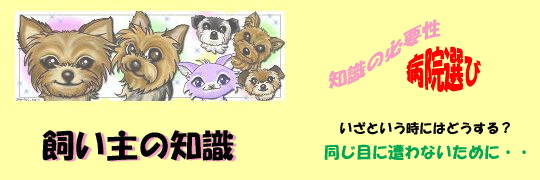 |
|
|||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
1) �z���ɂ��āE�z�����a�C 2) �������@������̕a�C 3) �̑��̕a�C 4) �_�o�̕a�C 5) �S���̕a�C 6) �畆�̕a�C 7) �t���E��A��̕a�C 8) ���t�̕a�C �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ȉ��́A�u�������䂭�b�コ���i��{�O�璘�j�v���A���Q�l�ɂ��Ă��܂��B 1) �z���ɂ��āE�z�����a�C �y�z���̌����z �z���́A�傫������̌���������A�a�C�×{�����z�����N�������ꍇ�A�܂��A���̕a�C���������ƂȂ��Ă��邱�Ƃ������悤�ł��B ���̑O�G����Ȃ��i���ۂ͉������ɃT�C��������͂��j�A�����Ȃ��z�����N�������ꍇ�A�l�����邱�Ƃ͊T�ˈȉ��̒ʂ�ł��B �i�����ɂ�����Ǝv���܂��j �@�@�@1�j�]�̋@�\��Q�@�i�������Ă�j �@�@�@2�j�ጌ���@�i�z���s�ǁA�C���V�������ʂ��K���łȂ��Ae.t.c.�j �@�@�@3�j������Ca�ቺ�@�i�z���s�ǁACa�ێ�ʕs���A�Y��Ae.t.c.�j �@�@�@4�j�����A�����j�A�Z�x�̏㏸�@�i�A�ŏǁA�喬�V�����g�Ae.t.c.�j �@�@�@5�j���ǁA�O���A��ᇓ��̌����@�i�������Ă�j �@�@�@6�j�����ǁ@�i���W�X�e���o�[�A�L�`�����������Ae.t.c.�j �@�@�@7�j���ŏǏ�@�i����A�K�ށA�`���R���[�g�Ae.t.c.�j �@�@�@8�j��̕���p �@�@�@9�j�����ǁ@�i�]�����͂̏㏸�ɂ��j ��ߐ��̂��Ƃ�����܂����A�a�C�Ɍq�����Ă��邱�Ƃ������̂ŁA���܂��Ă��炷���ɕa�@�Őf�Ē��������������Ǝv���܂��B ��ߐ��̂��̂��A�a�C�ɂ����̂��́A�z���̕p�x�Ŕ��f�ł���悤�ł��B �x�X�i�����`1�T�Ԓ��x�j������N�����悤�Ȃ�A�d�Ăȕa�C�̉\���������A�J��Ԃ�������N�����Ȃ���A��ߐ��̉\���������悤�ł��B �y�z���̗l�q�z �z���̗l�q�́A��T�͐�10�b�`�����̔���̌�A���܂��ăP���b�Ƃ��܂��B ���̍ہA�l����L���đ̂炵�A���ցE�E������ꍇ������܂��B �ċz���}�Ɏ~�܂����悤�Ɍ�����ꍇ������܂��B �i�������ŏ����z�����N���������������ł����B�B��u�A����ł��܂����悤�Ɍ����܂��B�B�j (1)�S�g���� �k�O���s���l �@�@�@�@�s���ȗl�q������A�����������Ȃ��A�悾��𐂂炷�A�q�f����Ae.t.c. �k�Ǐ�l �@�@�@�@�ˑR�A�l�����s�[���ƐL�тāA���]��������ւ̂��������肵�āA��������ׂ����K�^�K�^�Ɛk�킹��B �@�@�@�@�i�葫�̋��L�^���⌢���������ĉj���悤�ȉ^���������ꍇ������B�j �@�@�@�@�ӎ��������A��̓��E�͊J���A���ւ�����E�������������A�𐁂����肷��B �@�@�@�@���\�b����2�`3���ԑ�������A�P���b�ƕ��i�̏�Ԃɖ߂�����A���炭�����낤�Ƃ�����ɂ��ʂ̏�Ԃɖ߂����肷��B �@�@�@�@�i�d�x�̏ꍇ�͒Z���Ԋu�ʼn��x���J��Ԃ��j ���E�E���܂��ɉ����̏Ǐ�ł��B�B (2)�������� �k�Ǐ�l �@�@�@�@�]�̋�����ԂŋN����A�̂̓������i��]�̂ǂ̕�����������ԂɂȂ邩�ɂ���āA�z���������ꏊ���قȂ�B �@�@�@�@�i�Ⴆ�ΑO���������Ƃ𖽗߂��Ă���]�̕�����������������ƁA�O���������z������j �@�@�@�@�ӎ��Ɋ֘A����ꏊ�̔]�����������ꍇ�ł́A�Ăт����Ă��������Ȃ�������A�i�����Ⴍ�j�^���i�������ޓ���j�����z���A �@�@�@�@��ʂ̂悾��A�U���i���E���J���j�Ȃǂ��N����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���ȏ�(1)(2)�́A�A�C���X�y�b�g�h�b�g�R�������p�l �y�z���̎�ށz �z���́A���̔���̏�Ԃɂ���Č������ʂ��������悤�ł��B �@�S�g���z������ꍇ�A�A�̂̈ꕔ�݂̂̏ꍇ�E�E�ł��B �@�S�g���z������ꍇ�i�S�g����j �@�@�@�@�@�@�i�]���܂݁j�]�ȊO�̑��펾���A����A���łȂǁA�z�����N���������S�Ăɓ��ěƂ܂�܂��B �@�@�@�@�@�@��ߐ��̑��A�d�Ăȕa�C�̏ꍇ������̂ŁA���}�Ɍ������K�v�ł��B �A�̂̈ꕔ�݂̂̏ꍇ�i��������j �@�@�@�@�@�@�]�̋�����ԂȂǂŋN����܂��B �@�@�@�@�@�@�������ߐ��̏ꍇ�̑��A�]���ُ̈�i��ᇁA�����ǂɂ����́A���ǂُ̈�Ȃǁj���l������悤�ł��̂ŁA �@�@�@�@�@�@�����������������Ǝv���܂��B �@�@�@�@�@�@�����A�]���ُ̈�Ȃ̂ŁACT��l�qI�łȂ���Δ���Ȃ��i����ł�����Ȃ��ꍇ������悤�ł����E�E�j�ꍇ������悤�ł��B �@�@�@�@�@�@�z�����N���������ʂɂ���āA�]���̂ǂ̕����Ɉُ킪���邩�̔��f���ł���悤�ł��B �y�z���̑Ώ��z �z������̊Ԃ́A�u��o���������A���܂�܂Ō����v�����Ȃ��悤�ł��B ����Ɏ���o���Ċ��܂ꂽ��A�]�v�ɋ�ɂ�^���Ă��܂��\�������邩��ł��B ���u�����������Œ������Ȃ��悤�A��������o���v�Ƃ����Ώ��@������悤�ł����A�٘_����������Ƃ������悤�Ȃ̂ŁA �S�z�ȕ��́A�����ɏb��ɓd�b�Ŏw�������̂������Ǝv���܂��B �u�z���͂����Ɏ��܂�v�Ƃ����̂����ʂ̂悤�ł����A���������ꍇ�A�q��ł͂���܂����̂ŁA�����ɕa�@�ɓd�b���āA�w���������Ƃ��K�v�ł��B ����ɂ��Ă��A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�Q�Ă��A�������Ȃ��v�u�b��̎w�������v�u�a�@�ւ����ɘA��čs���v �E�E���Ƃ���ł��B �z���Ɍ��炸�A�ً}���Ԃɔ����A�u�b��ً̋}�A��������炩���ߋ����Ē����Ă����v���Ƃ���ł��B �y�z���̎��Áz 1)�Z���ԂŌJ��Ԃ����삪�N����ꍇ�A�]�̕a�C���������Ă���ꍇ �ˍR��������i�t�F�m�o�[���A�W�A�[�p���A�L���J���E���A�Ȃǁj �@ �������ڂ̂�����T�����߁A���x����̎�ނ�ς���ꍇ������B 2)�z���̌������������Ă���ꍇ �˂��ꂼ��̎����̎��� �@ ���z���ɑ��Ắu�ΏǗÖ@�v�i�z���̎��Âł͂Ȃ��A�z���̌��������̎��Â� �@�@�@����j�ɂȂ�܂��B �y�a�@�Ɋ|�����ċC��t���邱�Ɓz �����ɂ��āA�b��t���炵������������邱�Ƃ��K�v�ł��B �u�����͉����H�v�ɂ��āA�b�ォ��������A�S�z�Ȃ�Z�J���h�I�s�j�I����A�������f���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ邩������܂���B ���t�����Łu���ׁA�l���ǂ����������v���T���Ă������Ƃ��ł���A�����Œ��ׂ���A�Z�J���h�I�s�j�I���̍ۂɖ𗧂��܂��B �u�z�����N����������A�R�z����𓊗^�v�E�E�́A���v�̂悤�ł��B �R�z����́A�u�]�_�o�ɍ�p����v��ł����āA�Ⴆ�A�������u��J���V�E�����ǁv�������ꍇ�A�J���V�E���̕⋋�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��ł��B �����������ɂ���āA���Â͐T�d�ɂȂ�˂Ȃ�܂���B ����������Ȃ�����ǁA�u�R�z������������ꂽ�v�ꍇ�A ����́u�ΏǗÖ@�ł��邱�Ƃ�Y��Ȃ��v�E�E�悤�ɂ��Ē��������Ǝv���܂��B ���ɖ���z�����J��Ԃ��Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ă��A���������́u�i�s���Ă����v�ꍇ������܂��̂ŁE�E �����Ȃ�䂪�q���z�����N���������ɂ́A�����炭�w�ǂ̕��͗�Âł����Ȃ��Ǝv���܂��B �ł����A�Ȃ�ׂ���ÂɂȂ�A�u�����Ɍ�����˂��~�߂�悤�A�b��ɋ����v�]����v���Ƃ�Y��Ȃ��悤�ɂ��Ē�����Ǝv���܂��B �u�z���̌���������܂ň��S���Ă͂����Ȃ��v�ƁA���͎v���܂��B �y�z���̌��������̊m��z �z�����N�������Ƃ��A�����Nj��̂��߂̌����ɂ́A���悻���L�̂��̂�����悤�ł��B �@�@�@�@���t���� �@�@�@�A�A���� �@�@�@�B�����ǂ̍R�̌��� �@�@�@�C�G�R�[ �@�@�@�D�摜�����i�����g�Q���ECT�EMRI�j ���ʁA�܂��ŏ��ɂ��邱�Ƃ́A���t�����ɂȂ�܂��B �z���̌����͗l�X�Ȃ̂ŁA�����Ɍ�����˂��~�߂��邩�ǂ������d�v�ɂȂ�܂��B �ȑO�������悤�ɁA���t�����̍��ڂɂ���ẮA�u���Ȃ��v���Ƃ�����܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B �a�C�×{���̏ꍇ�́A���̕a�C���������ƂȂ��Ă��邱�Ƃ������悤�Ȃ̂ŁA���悻�����̌������t���Ղ��Ǝv���܂����A �}���z�����N�������ꍇ�́A�u�����\���v�̌����́A��x��ɂȂ��Ă��܂��\���������Ȃ��Ă��܂��܂��B�B �}���z���ő����̂́A�u���Łv�u�ጌ���v�u��J���V�E�����ǁv�̂悤�ł��B ���t�����Œ��ׂ鍀�ڂƂ��ẮA �@�@�@�E�����l �@�@�@�E�����J���V�E���iCa�j �@�@�@�E�������iWBC�j �@�@�@�E�Ԍ����iRBC�j�@�E�E���̑��ł��B ���ł̏ꍇ�́A�̋@�\�ɏ�Q���N�������Ƃ�����A �@�@�@�EGPT�AALT �@�@�@�EGOT�AAST�@�E�E�E���ꂩ�ׂ܂��B �@�`�C�ł̌����ňُ킪�����Ȃ��ꍇ�ACT��MRI�i��ᇓ��̔����̂��߁j�A�]�Ґ��t�����i�������Ă�j�����Ċm��f�f���s���悤�ł��B ���̏ꍇ�́A�����̌l�����a�@�ł͂��̏�łł��Ȃ������̂��߁A��w�a�@�Ȃǂł̌����ɂȂ�܂��B ��������̕a�@�ŁA�u�����ɂُ͈킪�Ȃ��̂ŁA�l�q���݂ĉ������v�ƌ���ꂽ�ꍇ�A��ߐ��̂��̂ł���Ηǂ��̂ł��� �i���˂Ⓤ��ȂǂŎ���ł��傤����j�A���̌���o�߂��ǂ��Ȃ��ꍇ�́A���}�ɑ�w�a�@���ō��x�Ȍ��������������ǂ��Ǝv���܂��B �ꍏ�𑈂��������ƁA�F�����������ǂ��Ǝv���܂��B 2) �������@������̕a�C �y������̎����Ƃ́H�z �����厾���́A���̕a�C�ɔ�ׁA�����ƌ����Ă���悤�ł��B �u�����厾�����z����������ُ̈�v�E�E�ł��B �z�������傷���Ȋ튯�́A�u�b��B�v�u���t�v�ł��B �y�����厾���̑�\�I�Ȃ��́z �b��B�E���t�ɂ��z�������ُ펾���̑�\�I�Ȃ��̂́A�ȉ��ɂȂ�܂��B �b��B�ˍb��B�@�\���i�ǁi���命���j�A�b��B�@�\�ቺ�� ���t�˕��t�玿�@�\���i�ǁi���命���A�N�b�V���O�nj�Q�j�A���t�玿�@�\�ቺ�ǁ@�E�E�����āA���A�a�ł��B ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �y�N�b�V���O�nj�Q�z ���R�����̏ꍇ�ƁA�㌴���i�X�e���C�h�ɂ���Q�j�̏ꍇ�ɕ�������悤�ł��B ���Ǐ� �R���`�]�[���Ƃ����A�X�e���C�h�z�������̉ߏ�ɔ����l�X�ȏǏ݂���B �i���E�Ώ̂́j�E�сA���H�A�얞�A�������A�A���C�́A���C���Ȃ��Ȃ�A �������c��ށi���������B�G�R�[�ł��ُ�m�F�ł��Ȃ��j�A�уc���������Ȃ�E�E�ȂǁB �����R�����ƈ㌴�� ���R�����˔]�����́E���t�̎�ᇁA���t�ُ̈�ɂ�� �㌴���˃X�e���C�h�̉ߏ蓊�^�A�������^�ɂ�镛�t�̈ޏk ���㌴�����ǂ����̔��� �h���z�������𒍎� ���R�����˃X�e���C�h�z�������̕��傪�����i���t�̈ޏk�Ȃ��j �㌴���ˁ@�@�@�@�@�@�@�V�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ��i���t�̈ޏk����j ������ ���R�����˕��t�̎�ᇂ͊O�Ȏ�p�A�]�����̂̎�ᇂ͎�p������� �㌴���ˏ��X�ɃX�e���C�h�̓��^�����炵�A���t�@�\�������� �����R�������N����Ղ����� �v�[�h���A�_�b�N�X�t���g�A�r�[�O���A�{�X�g���e���A�A�{�N�T�[ ��8�Έȏ�ł̔��ǂ����� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �y�b��B�@�\�ቺ�ǁz ������ �Ɖu�ɂ��b��B�̔j��A�܂��͌����s���̍b��B�̈ޏk�ɂ��B �b��B�g�D�̔j��܂��͈ޏk��75%���z����ƏǏ����B ���Ǐ� �u�ǂ�ȕa�C�ɂ��݂���v�Ƃ����Ă���قǁA�Ǐ�͗l�X�B �u�N�̂����H�v�Ǝv��ꂪ���ȏǏ�Ƃ̂��ƁB �@�@�E�{�[���Ƃ��Ă���B�������݂��A������B�����������B �@�@�E�E�сi��Ώ́A�Ǐ��I�j�A�уc���������B �@�@�E�畆�̉��� �@�@�E�H�~�s�U�B�H�ׂĂ���ʂ̊���ɑ����Ă���B �@�@�E�ǂ��Ȃ�����A�����Ȃ�������J��Ԃ��B ���m��f�f���@ ���ː��Ɖu�R�̑���@�i�b��B�z����������j �����A�a�A�N�b�V���O�nj�Q�A�A�W�\���a�A�t�����A�̎����C�e��畆���A�����p��Ȃǂł��b��B�z�������͒ቺ���邽�߁A �����I�Ȕ��f��v����B ������ �b��B�z���������܂̓��^ ���m��f�f��łȂ��ƁA�t�ɘ��i�i��������j�ǁi�z�������ߑ��j�ɂȂ��Ă��܂��̂Œ��ӁB ���L�ɂ������u�b��B�@�\���i���́A�u�ڂ��M���M�����Ă���v�悤�Ɍ����A�����Ă����ƐS������̊댯������B �����a���Ղ����� ��5�`6�Έȍ~�̒��^���A��^���ɑ����i�g�C��A�~�j�`���A��̔��a�͋H�j �������A��D�ς݂̎q�ɑ����B �O���[�g�f���A�I�[���h�C���O���b�V���V�[�v�h�b�O�A�h�[�x���}���A�_�b�N�X�t���g�A�A�C���b�V���Z�b�^�[�A�~�j�`���A�V���i�E�U�[�A �S�[���f�����g���o�[�A�{�N�T�[�A�R�b�J�X�p�j�G���A�G�A�f�[���e���A ���ڂ����́ˁu�b��B�@�\�ቺ�ǂƂ����a�C�������m�ł����H�v �b��B�@�\�ቺ�ǂ��ǂ����̊ȒP�ȃ`�F�b�N������悤�ł��B �˗��u�����a�@HP�@�u�b��B�@�\�ቺ�ǂ̎��Ȑf�f�X�R�A�v ���̕a�C�́A�b�オ�����Ƃ����A�w��ł�������ACT�Ȃǂ̐ݔ����s�v�Őf�f�����Â��ł���悤�ł��B ������x�̔N��ɂȂ��Ă��甭�ǂ��A�H�~���M���M���܂ŗ����Ȃ����߁A �u�a�C�炵�������Ȃ��v�u�N�̂����v�E�E�Ɗ��Ⴂ���Ă��܂������ȓ_�������ł��ˁB�B �z�������܂����ݑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���i�ǂɂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��_�͓��A�a�̎��ÂƎ��Ă���悤�ł����A �����C�t���A�u���C�����߂��A�������ł���v�悤�ł��B ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �y�����厾���̕������z �b��B�E���t������z�������́A�̂̂�����y�f�����ɊW���Ă��邽�߁A�����̃z����������Ɉُ킪����ƁA ���낢��ȉe��������悤�ł��B �����āA�u�킩��ɂ����v�a�C�Ɋ|����P�[�X�������悤�ł��B �����킩��ɂ����̂��H ���ǂ��Ă��A�u�H�~���Ȃ��Ȃ�Ȃ��v�E�E����Ƃ̂��ƁB�B �a�C�̃T�C���̑�\�I�ȏǏ�ɁA�u�H�~���ށv������܂��B �H�~���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ́A�l�Ԃ��܂߁A�ǂ̓����ɂƂ��Ă��ُ킪�l�����܂����A�u�H�~�ɕω��������v���Ƃ���A��������������̂ƁA �b��������Ƃ������ɂȂ�E�E�炵���ł��B �����ƕς�炸�ɐH�~���������̂ɁA�}�Ɍ��C�������Ȃ��Ď���ł��܂����Ƃ�����A�̂́u�����v�ŕЕt�����Ă������Ƃ����������悤�ŁE�E �y��ɂ��i�㌴���j���ǂɂ��āz �A�g�s�[�ȂǂŃX�e���C�h�̓��^�i���ݖ�A�h���j���Ă���ꍇ�A�㌴���̃N�b�V���O�nj�Q�ɂȂ�Ղ��悤�ł��̂ŗv���ӂł��B �b��̊Ԃł��A�u�X�e���C�h�𑽗p����b�オ�����A�㌴���̃N�b�V���O�nj�Q������Ă���v�Ɣᔻ���Ă����������悤�ł��B �畆���̎��Â̂��߂̃X�e���C�h��ł����A�N�b�V���O�ɂȂ�A�畆���ɂ��Ȃ�Ղ����߁A�u���Â��Ă���͂����A�X�Ɉ����v������ꍇ������Ƃ̂��ƁB�B �㌴���ŁA�X�e���C�h�̓��^�ʂ����炵�A���t�@�\�������鎡�Â��s���ꍇ�ɁA�����傪���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɓ��u����݂������A ���������悤�Ɍ�����̂ŁA���̊��Ԃ�ς��邱�Ɓv�E�E�������ł��B ���t�@�\������A�����ŃX�e���C�h�z�������傷��̂ŁA����ɗǂ��Ȃ��Ă����悤�ł��B �N�b�V���O����������ƁA���A�a�ɂȂ�ꍇ������A�䂪�Ƃ̏t�V�i�̂悤�ɖ����C���V�������𒍎˂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��E�E ���A�a�͂����m�̒ʂ�A�������邱�Ƃ͂Ȃ��A������Ȃǂ̍����ǂ�����A���܂��R���g���[���ł��Ȃ��Ǝ��Ɏ��鋰���a�C�ł��B�B �b�ォ��X�e���C�h�𓊗^�����ꍇ�́E�E �@�@�E�ǂ�ȗ��R�Ŏg���̂� �@�@�E���^�̃X�P�W���[���i�n�߂͑����A����Ɍ��炷�̂����ʁj���B �E�E���Ƃ��厖���Ǝv���܂��B �㌴���̃N�b�V���O�ɂȂ�Ă��ꂽ��A��k����Ȃ��ł����̂ˁE�E �R) �̑��̕a�C �y�̑��̎����Ƃ́H�z �̑��́u���ق̑���v�ƌĂ��̂͂����m�̒ʂ�ŁA�u���Ȃ舫������܂ŏǏo�Ȃ��v�Ƃ������ȑ���ł��B ���̔��ʁA�u�Đ��\�́v�ɒ����Ă��鑟��ł�����A���ɖ߂邱�Ƃ����҂ł������̂ł�����悤�ł��B �̑������ł́A�u��ᇁE���ǁv�u�i���ł̂悤�Ɂj�̍זE���j�����́v�E�E�Ƃ������������ł���悤�ł��B �y�̎����̑�\�I�Ȃ��́z ����(���j�ɑ����ƌ�����a�C�A�u�喬�V�����g�v�ɂ��āB ���̕a�C�ŋꂵ��ł���q�Ǝ�����̕��͑����悤�ł��B �喬�Ƃ́A�u���Ɗ̑����q�����ǁv�̂��Ƃł��B �V�����g�Ƃ́A�u�o�C�p�X�v�̂��ƂŁA�喬�V�����g�́A�u�喬�Ƀo�C�p�X���o���Ă��܂��v�a�C�ł��B ������z�����ꂽ�h�{�ƁA���ނȂǂ��甭������A�����j�A��K�X�A���̑�������������G�ۂȂǂ́A���˖喬�ˊ̑��ւƑ����A �s�v�Ȃ��̂͊̑����h�߂���āA���ꂢ�Ȍ��t���̓����z����悤�ɂȂ��Ă��邻���ł��B �喬�V�����g�̏ꍇ�A�̑���ʂ�Ȃ��o�C�p�X���ł��Ă��܂����Ƃɂ��A�̑��̋@�\���g�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A �A�����j�A��̂Ɉ������̂����ڌ��t�ɍ������Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �y�喬�V�����g�z ������ 1)��V�� 2)�㔭�̂��́i�喬�̈����������߂Ƀo�C�p�X���ł���j ���Ǐ� �i�̑����g���Ă��Ȃ����߁j�̕s�S�̏Ǐ���B �@�@�@�E�̐��]�ǁi�A�����j�A���̓őf���]�ɍs���j �@�@�@�E�̑����i�̑��Ɍ��t������Ȃ����Ƃɂ��@�\�ቺ�j �����ǂ̓��� �H��i���ɓ��ނ�H�ׂ���j�ɏǏ����B ���炪�����A�ُ�ɑ����Ă���B �@�@�@�E���C������ �@�@�@�E�N�T��� �@�@�@�E���\�� �@�@�@�E�ڂ������Ȃ��Ȃ� �@�@�@�E�z���i�Ă�ƍ����j�E�E�E�Ȃ� ���f�f �J���[�G�R�[�ɂ��ڎ��f�f ���t�����i�����A�����j�A�Z�x�Ȃǁj ������ ��p�i�喬�V�����g�̕ǎ�p�j ���p��̌o�߂��ǂ���A�������͍��� �����a���Ղ����� �@�@�@�E���[�N�V���[�e���A �@�@�@�E�~�j�`���A�V���i�E�U�[�@�Ȃ� �����a���� ����2�A3����������6�������܂ł������B ��V���̂��Ƃ��������߁A���ʐH�ɐ�ւ��������甭�ǂ���悤�ł��B ��p�����Ȃ���A����Ȃ��a�C�̂悤�ł��B �z����ُ�s���ȂǁA�_�o�ǏłȂ��Ɣ�������A�܂��c�����ɑ������Ƃ���A�u�W�X�e���p�[�v�⑼�̕a�C�ƊԈ����ꍇ������Ƃ̂��ƁB �����̎�p���K�v�Ȃ̂ŁA�f�f�����Ȃ����Ƃ��ƂĂ��d�v�̂悤�ł��B ��p���̂��̂́A�V�����g�i���ǁj���Č������~�߂邾���̂悤�ł����A�V�����g�̂���ꏊ�ɂ���ē�Փx�E�������͈Ⴂ�A �V�����g���̑��̊O�ɂ���ꍇ�͐������͍����A�̑��̓����ɂ���ꍇ�͓����p�ɂȂ�悤�ł��B ���ǂ̎�p�ɂȂ邽�߁A��w�a�@���A����Ȃ�̕a�@�E�o���̂���b��t�̉��Ŏ�p���邱�Ƃ��K�v�̂悤�ł��B ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �y�̑��̎�ᇁz ���ɑ�����ᇂ́u�̍זE�K���v�A�L�ɑ����̂́u�_�ǃK���v�Ƃ̂��Ƃł��B �����A�������͂��قǍ������̂ł͂Ȃ��悤�ł��B �̑��̏ꍇ�A��ᇂ̂ł���ʒu�ɂ���ďǏقȂ�A �@�@�@�̑��̒[�ɂł����ꍇ�A�Ǐ�͌���Ȃ��B �@�@�A���t�z�̎�v�ȕ��ʒ���_�̂��ɏo�����ꍇ�A�̋@�\�s�S���N�����@�@�E�E�悤�ł��B ��ᇂ̂ł����ɂ����낢�날��A �@�@�E�傫�Ȃ��̂���ł��� �@�@�E�̑������Ɋ���ł��� �@�@�E���ڂ��n�b�L�����Ȃ��悤�ɍL����@�E�E�ȂǂƂ̂��Ƃł��B ��p�Ŏ�邱�Ƃ̂ł���悤�Ȃ��̂ƁA�����łȂ����̂ƂŁA�^�����n�b�L����������悤�ł��E�E �̑��\�ʋ߂��ɑ傫�Ȏ�ᇂ��o����ꍇ�A �����i����̉��ӂ�j��G��Ίm�F�ł��邱�Ƃ������悤�Ȃ̂ŁA���܂Ƀ`�F�b�N���邱�Ƃ��K�v��������܂���B �̑��̂ǂ��Ɏ�ᇂ��o�����Ƃ��Ă��A���̑���ɔ�ׂāu�Ǐo�Ȃ��v�悤�Ȃ̂ŁA��������������Ȃ悤�ł��B�B �u�Ǐo�Ȃ��v�傫�ȗ��R�́A�u�̑���8�����x�̋@�\�������Ă��A�̕s�S�ɂȂ�Ȃ��v����Ƃ̂��ƁB �̕s�S�̏Ǐo���Ƃ��ɂ́A���Ȃ�[���ȃ_���[�W������\���������悤�ł��B�B ������G���Ċm�F�ł����ꍇ�́A�܂��K�^�Ȃ̂�������܂���ˁB�B ���������ɂ��ẮA�u�G�R�[�ɂ��f�f�v���L���̂悤�ł��B �l�ԂƓ����ŘV���ɂ���ăK���̔������͍��܂�悤�Ȃ̂ŁA���ɘV���̈�i6�Έȏ�j�ɂȂ�����A�N1��͌��N�f�f���A �G�R�[�ɂ���đ���i���Ɋ̑��E�t���j�̃`�F�b�N�����邱�Ƃ��]�܂����̂ł��傤�B ��ᇓE�o��p�̏ꍇ�B ���̊̑���6���̗t��ɕ�����Ă��邻���ŁA�u��ᇂ̖���������@���Ɏc�����̔��f���d�v�v�Ƃ̂��ƁB �̑��́A�Ƃ����̂����ۂ̂悤�ɁA�Ȃ�Ɓu�����Ă���i���ɖ߂�j�v�����ł��I �̑���3/4��E�o���Ă��A���̏ꍇ�A8�T�ԂŌ��ɖ߂�Ƃ̂��ƁB�i�������I�j ���ɖ߂�܂ł̊ԁA�̋@�\��ۂ��߂ɁA�u�@���ɗǂ��Ƃ�����c�����v�E�E�������ł��B ��p�ɂ���Ď�ᇂ��S�Ď��A�̑����Đ�����A�����ł���悤�ł��B ��ᇂ���邽�߂ɁA�u���������ł��邩�ǂ����v�A�����āu�ŏ����̓E�o�v�E�E�������ꓹ�̂悤�ł��ˁB �̕s�S�̏ꍇ�A�ڂɌ����镪����Ղ��Ǐ�́u���t�v�ł��B ���ڂ�畆�A���̔S���Ȃǂ����F���Ȃ�̂ł����ɕ�����͂��ł��B �̑����@�\���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�őf���̒��ɉ���Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B �q�f�A�������A�A�����A���C�r���A�z���i�̐��]�ǁj�E�E�Ȃǂ̏Ǐ����悤�ł��B �̑��͂��Ȃ�̃_���[�W�������Ă��Đ�����Ƃ������ƂȂ̂ŁA���B������ɂƂ��ẮA�ق�̏����A�~����C�����܂��B ����ǂ���ς�A���������E�E�d�v�ł��ˁB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�f���� �@�@�@ �@�f���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�Ǘ��l�ւ̃��[�� �@�Ǘ��l�ւ̃��[�� |
||||||
|
Top
Copyright © 2007 haru. All rights reserved.
|
||||||
